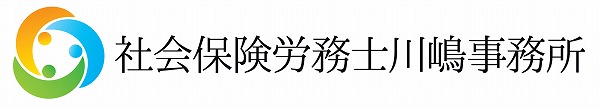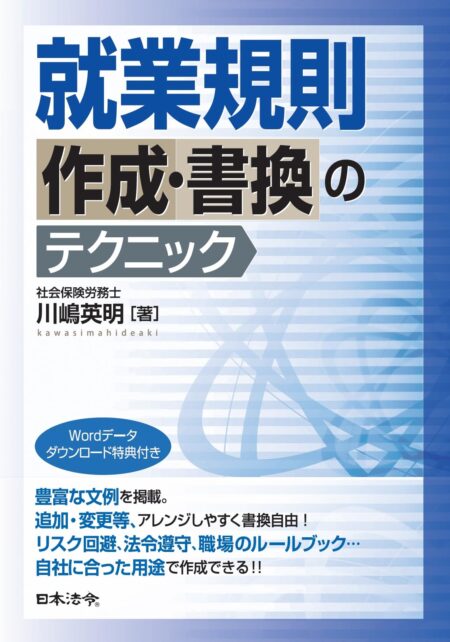自分の会社の従業員が、急病や怪我、メンタルヘルス不調等で長期間労務不能となって困ったという経験、長く会社を経営していると、会社の規模を問わず、一度はあるのではないでしょうか?
仮に、これまでなかったとしても、メンタルヘルス不調を訴える労働者は年々増えているため、今後も絶対にないとは言い切れません。
こうした、長期の労務不能が見込まれる場合に活用させるのが「休職」という制度です。
休職とは何らかの事情により、会社の業務に就くことができない労働者に対し、会社に籍を置いたまま労働を免除する制度となります。
この休職制度ですが、めったに利用されないこともあり、会社の実態とかけ離れた制度となっていることも少なく、いざ必要となった時に休職を巡って労使間でトラブルになることもあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐ、あるいはトラブルが起こった際になるべく穏便にことを収めるためにも、この記事では就業規則の「休職」の条文作成のポイントと規定例について解説していきます。
この記事の目次
1. 条文の必要性
休職は相対的必要記載事項の「その他」に当たります。
つまり、休職制度が会社にあるなら、休職の規定は必ず定めないといけないわけです。
2. 休職の法律・制度上のポイント
2.1. 休職は法律で定められた制度ではない
時間外労働や年次有給休暇と違って、休職は法律上に定めのない制度です。
そのため、制度構築の会社の裁量の範囲は大きくなっており、極論を言えば、休職制度を定めないことも可能です。
とはいえ、労務管理や企業秩序の面をトータルで考えた場合「定めないはない」制度ですし、またいくら会社の裁量の範囲が大きいとはいえ、常識の範囲を超えるような制度とすることはできません。
2.2. 休職制度を定める意義
なぜ、休職制度を「定めないはない」かというと、休職制度がない会社であっても、休職に準ずる扱いをせざるを得ない場合があるからです。
例えば、私傷病により長期の休業を余儀なくされた場合、休職規定がないからといって、労務の提供ができないことを理由に直ちに解雇したとしても、司法上は不当な解雇と判断される可能性が極めて高くなります。
そのため、休職規定がない場合であっても、個別の対応として、一定の欠勤を認めるといった措置が必要となるわけですが、であるなら、事前に休職制度を整えておいた方が、会社に有利な制度設計ができるわけです。
なにより、休職制度がきちんとあって、休職期間を満了したにもかかわらず復帰できないとなれば、司法上、正当な解雇と認められる可能性は高まるので、休職制度を「定めないはない」わけです。
2.3. 休職は会社の業務命令によって行われるのが前提
たまに勘違いされている方がいますが、休職は労働者の当然の権利ではありません。
そのため、休職は年次有給休暇のように労働者が請求するものではなく、会社が休職を命じるのが原則であり、休職の条文を定める場合も、「労働者の申請」ではなく、あくまで会社が「休職を命じる」という形にしておきます。
一応、休職は法律上定めのある精度ではないので「労働者の申請」ありきにすることもできますが、それはあくまでも「できるだけ」で、会社から見た場合、そうする必然性はありません。
3. 休職条文作成のポイント
3.1. 休職規定の分割
このサイトでの「休職」の条文は、
- 休職(休職事由)
- 休職期間
- 休職期間中の取扱い
- 休職中の報告
- 復職
の5つに分割しています(このうち「休職中の報告」「復職」については別の記事で解説を行っています)。
もちろん、これは一例ですので、この通りにする必要はありません。
実際、他の規定例は、上で分けた5つを全て一つの条文にまとめていたり、私傷病休職と他の休職を分けていたりするなど、規定を作る人によってその形式は様々です。
条文例の作成者としては、休職の一連の流れに沿った方がわかりやすいと考え上記のように分けていますが、これだとわかりづらい、イメージしづらい、ピンとこない等々の場合は、他の規定例を見てみるのも良いでしょう。
参考:休職関連の条文作成のポイントと規定例
3.2. 私傷病休職とその他の休職
休職事由には私傷病などの労働者の都合によるもの、他の会社に出向した労働者を休職扱いとする場合のように会社の他の制度との兼ね合いによって設けるもの、さらには裁判員に選出された場合のようにどちらの都合ともいえない事情が生じた場合に対応するものに分けることができます。
出向などのように休職事由や休職期間がはっきりとしているものは、労使間で問題となることはほとんどありません。休職期間の終わる時期が予定できるうえに、ほぼ間違いなく復職が可能だからです。
一方、私傷病休職に関しては、その事由の存在期間がいつからいつまでとはっきりしないことが多く、復職時に問題を生むことも少なくありません。
そのため、休職に関する規定で最も注意すべきは私傷病休職であり、私傷病休職に関する部分については慎重にルール決めする必要があります。
私傷病休職を命令する場合の欠勤期間
記事の最後に挙げている規定例では、休職を命令するかどうかを判断する欠勤期間について、
- 業務外の同一または関連する傷病による欠勤が休日を含め連続で1か月を超え、または過去2か月の欠勤日数が通算20日を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
- 出社はしているものの、業務外の傷病により労務の提供が不完全なとき
と定めています。
これは、例えば、休職の要件に「連続で「か月欠勤が続いた場合」だけ定めてしまうと、1か月連続で欠勤していないと休職できない、といったことが起こりうるため、それを回避するためです。
なお、欠勤期間の「1か月」や「過去2か月の欠勤日数が通算20日」というのはあくまで例であり、会社ごとの実態に合った期間を定めていただければいいのですが、短すぎると休職の判断を誤る可能性がありますし、長すぎると休職制度を設けている意味が薄れてしまいます。
そのため、休職事由に合わせた適切な期間を設定すべきといえます。
私傷病休職の休職期間
出向などのように、休職する期間がはっきりしているものについてはその期間分を休職扱いとすれば問題ありません。
しかし、私傷病休職のようにいつまでとなるかはっきりしないものについては、会社がその期間を定める必要があります。
この私傷病休職の期間については法律上、明確な定めはありませんが3か月から1年程度の期間で定める会社が多いようです。また、休職期間は会社の規模が大きくなるほど長くなる傾向にあります。
その他、休職期間の長さについて、勤続年数によって差を設けることも可能ですが、いずれにせよ、会社にとって無理のない範囲で休職期間を定めるのが最優先です。
3.3. 休職事由の追加と削除
記事の最後に規定例で挙げている4つの休職事由は、あくまで一例です。
なので、出向がない会社では出向に関する休職事由は不要なので削除して構いませんし、逆に他に休職事由がある場合は、会社の実態に合ったものを追加していただければと思います。
なお、就業規則の規定例でときどき見られる「起訴休職」については、そもそも警察に身柄を拘束されていて長期間労務を提供できない場合、休職ではなく解雇の要件に当てはまるのではという議論もあります。
そして、こうした考えに基づくと起訴休職の定めがあるが故に解雇ができないという事態も起こりえるため、本当に必要なのかどうか検討が必要でしょう。
3.4. 休職期間中の取扱い
休職の規定を定める場合、休職期間中の給与や勤続年数などの労務管理上の扱いを定めておく必要があります。
休職中の給与とノーワーク・ノーペイ
給与に関しては、休職事由にかかわらずノーワーク・ノーペイの原則から無給とするのが普通です。
なお、会社の判断で有給とすることも可能ですが、私傷病により休職する場合で、健康保険から傷病手当金が支給される場合、会社から給与が出ていると傷病手当金の一部または全部は支給停止とされてしまう点には注意が必要です。
休職期間と勤続年数の関係
次に勤続年数についてです。
休職期間を会社で定める制度の勤続年数に含めるかどうかも基本的には会社の裁量の範囲となります。
例えば、退職金の支払い要件や金額に勤続年数を定めている場合に、休職期間を含めるかどうかは会社の裁量で決めることができます。
一方で、年次有給休暇の付与日数を算定する際の勤続年数については会社に在籍している限り除外することはできません。このように、会社の都合で含める含めないを決められないものもあります。
社会保険料
1か月の給与がまるまるなくて、社会保険料を給与から天引きすることができない場合も、社会保険に入っている以上は、休職中の労働者の分の社会保険料は発生します。
この場合の労働者負担分の社会保険料は、会社が一旦立て替えて支払うのが普通ですが、中には立て替えた分を返さない労働者もいます。
立て替えた分を支払わない場合の社会保険料の請求については、就業規則に定めがなくても可能ではあるものの、あった方が就業規則の規定を根拠に請求しやすいため、下記の規定例ではその定めをしています。
4. 就業規則「休職(休職事由)」の規定例
第○条(休職)
- 従業員が、次の各号のいずれかに該当するとき、会社は所定の期間、休職を命じる。
① 業務外の同一または関連する傷病による欠勤が休日を含め連続で1か月を超え、または過去2か月の欠勤日数が通算20日を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
② 出社はしているものの、業務外の傷病により労務の提供が不完全なとき
③ 業務命令により他社に出向したとき
④ 前各号のほか、特別の事情があって休職させることを、会社が適当と認めたとき - 前項の命令は、復職が見込まれる従業員にのみ発令する。
- 1項1号または2号により休職する者については、休職期間中、療養に専念しなければならない。
第△条(休職期間)
- 第〇条の休職期間は次の期間を限度とし会社が定める。
① 第〇条■項1号、2号の場合(※) 6か月
② 第〇条■項3号、4号の場合 会社が必要と認めた期間 - 前項1号については情状により期間を延長することがある。
※ 私傷病休職を想定
第□条(休職期間中の取扱い)
- 第〇条■項1号、2号、および4号(※1)の休職期間における賃金は無給とし、原則として勤続年数には通算しない。ただし、年次有給休暇の付与日数の基準となる勤続年数には通算する。
- 第〇条■項3号(※2)に該当する場合、休職期間における賃金および勤続年数については、その都度定める。ただし、年次有給休暇の付与日数の基準となる勤続年数には通算する。
- 休職により賃金の支払われない期間の社会保険料の従業員負担分については、原則として、各月分を会社が立て替えた後に本人に請求するものとし、従業員はその請求月の翌月末日までに支払うものとする。
※1は私傷病休職、その他の休職を想定
※2は出向休職を想定
5. 規定の変更例
5.1. 私傷病休職の条件を変更する場合
第○条(休職)
- 従業員が、次の各号のいずれかに該当するとき、会社は所定の期間、休職を命じる。
① 業務外の同一または関連する傷病による欠勤が休日を含め連続で2か月を超え、または過去3か月の出勤率が3割に満たない場合で、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
② 出社はしているものの、業務外の傷病により労務の提供が不完全なとき
③ 業務命令により他社に出向したとき
④ 前各号のほか、特別の事情があって休職させることを、会社が適当と認めたとき - 前項の命令は、復職が見込まれる従業員にのみ発令する。
- 1項1号または2号により休職する者については、休職期間中、療養に専念しなければならない。
5.2. 休職事由を追加する場合
第○条(休職)
- 従業員が、次の各号のいずれかに該当するとき、会社は所定の期間、休職を命じる。
① 業務外の同一または関連する傷病による欠勤が休日を含め連続で1か月を超え、または過去2か月の欠勤日数が通算20日を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
② 出社はしているものの、業務外の傷病により労務の提供が不完全なとき
③ 業務命令により他社に出向したとき
④ 外国籍の者で一時帰国が必要なとき
⑤ 公務により労務の提供ができないとき
⑥ 組合専従職員となったとき
⑦ 自己研鑽のため会社の定める留学制度を活用する期間
⑧ 前各号のほか、特別の事情があって休職させることを、会社が適当と認めたとき - 前項の命令は、復職が見込まれる従業員にのみ発令する。
- 1項1号または2号により休職する者については、休職期間中、療養に専念しなければならない。
5.3. 勤続年数に応じて休職期間を変更する場合
第△条(休職期間)
- 第〇条の休職期間は次の期間を限度とし会社が定める。
① 第〇条■項1号、2号の場合 勤続年数1年未満 1か月
勤続年数1年以上3年未満 3か月
勤続年数3年以上 6か月
② 第〇条■項3号、4号の場合 会社が必要と認めた期間 - 前項1号については情状により期間を延長することがある。
5.4. 出向がない会社の場合
(規定例の出向関連の規定を削除したうえで号の番号を調整)
第○条(休職)
- 従業員が、次の各号のいずれかに該当するとき、会社は所定の期間、休職を命じる。
① 業務外の同一または関連する傷病による欠勤が休日を含め連続で1か月を超え、または過去2か月の欠勤日数が通算20日を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき
② 出社はしているものの、業務外の傷病により労務の提供が不完全なとき
③ 前各号のほか、特別の事情があって休職させることを、会社が適当と認めたとき - 前項の命令は、復職が見込まれる従業員にのみ発令する。
- 1項1号または2号により休職する者については、休職期間中、療養に専念しなければならない。
第△条(休職期間)
- 第〇条の休職期間は次の期間を限度とし会社が定める。
- ① 第〇条■項1号、2号の場合 6か月
② 第〇条■項3号の場合 会社が必要と認めた期間 - 前項1号については情状により期間を延長することがある。
第□条(休職期間中の取扱い)
- 第〇条■項1号、2号、および3号の休職期間における賃金は無給とし、原則として勤続年数には通算しない。ただし、年次有給休暇の付与日数の基準となる勤続年数には通算する。
- 休職により賃金の支払われない期間の社会保険料の従業員負担分については、原則として、各月分を会社が立て替えた後に本人に請求するものとし、従業員はその請求月の翌月末日までに支払うものとする。
6. 「もっと規定例を知りたい」「自分の会社に合った就業規則がほしい」方はこちらも!
目指したのは就業規則の参考書ではなく「英会話集」。
この本なら、多彩な規定例から会社の実態に合った規定を選ぶだけで、あなたの会社に合った就業規則が作成できます!