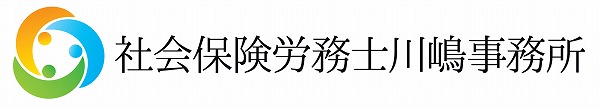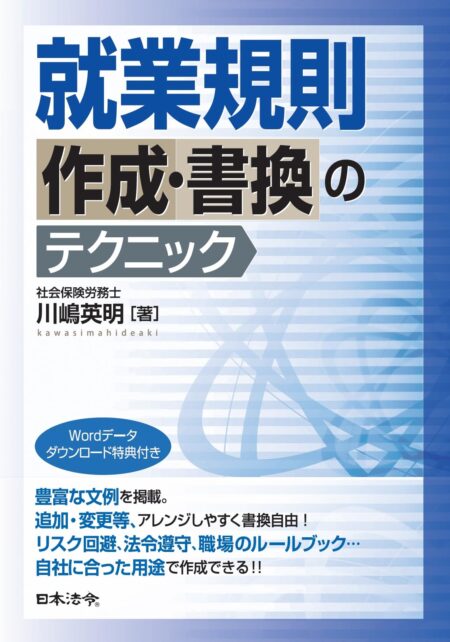解雇予告は労働基準法で会社に義務づけられているものです。
その内容から「1か月分の給与を払えば自由に解雇していい」と勘違いされがちですが、そうした理解は実態と大きくかけ離れています。
就業規則の観点からいうと、解雇予告の条文自体に注意点があるわけではないですが、運用面では気をつけることや、判断に迷う曖昧な部分も多いので、そのあたりを中心にこの記事では見ていきます。
この記事の目次
1. 法令から見た「解雇予告」のポイント
1.1. 解雇予告は会社の義務
解雇予告とは解雇の日の30日前の予告、もしくは平均賃金の30日分の予告手当を支給することをいい、解雇を行う際は会社の義務として、労働基準法に定められています。
ここでいう30日とは暦日のことをいい、休日や会社に休業日も含みます。
1.2. 解雇予告と予告手当の併用も可能
この30日前の予告と予告手当の支給は併せて行うことも可能で、例えば、10日分の予告手当を支給する場合、20日前の予告で義務を果たすことができます。
1.3. あくまで手続き
一方、解雇予告のよくある勘違いとして「1か月の給与を払えば会社は労働者を解雇できる」といったものがあります。
しかし、解雇予告はあくまで解雇を行う際の、手続上の義務に過ぎません。
解雇予告や解雇予告手当の支給を持って、その解雇の正当性が認められるわけではなく、事由によっては解雇予告を行っていたとしても不当解雇として労働者から訴えられる可能性はあります。
1.4. 解雇予告の対象外となる者
解雇予告はすべての労働者が対象外となるわけではなく、以下の者については適用されません
- 日々雇い入れられる者
- 2か月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者(採用後14日以内のものに限る)
1.5. 解雇予告除外認定
労働者の責に帰すべき理由
会社は、以下の場合で、所轄の労働基準監督署より認定を受けた場合、解雇予告を行う必要はありません。これを解雇予告除外認定といいます。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者に責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
ここでいう「労働者の責に帰すべき理由」とは具体的には以下の通りとなります。
- 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
- 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
- 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
- 他の事業へ転職した場合
- 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
出典:しっかりマスター 労働基準法-解雇編-(東京労働局)
基本的には懲戒解雇の場合に
解雇予告除外認定は、基本的には懲戒解雇の場合に行われるものですが、普通解雇でも対象となる場合はあります。
なお、解雇予告除外の認定は行政が行うものですが、解雇の正当性について判断するのは司法です。
そのため、行政が認定を出したとしても、裁判では不当と判断されることも、その逆で、行政が認定を出さなかったとしても、裁判で正当と判断されることはあり得ます。
諭旨解雇と解雇予告
諭旨解雇とは、労働者に対し会社が退職届の提出を勧告し、勧告に応じた場合、その労働者を解雇するものをいうとされています。
諭旨解雇は解雇という名称ではあるものの、実務上、諭旨解雇を行う場合、労働者に退職届を提出させて自己都合退職扱いとすることも多いので、解雇予告が必要かどうか判断に迷うところです。
ただ、いずれにせよ諭旨解雇を行う場合「労働者の責に帰すべき事由において解雇する場合」にあたる何らかの事由があると思われるため、解雇予告除外認定を受けることができると考えられます。
解雇予告除外認定を受けることができれば、解雇予告手当を支払う必要はないので、心配であれば解雇予告除外認定を受けた方がよいかもしれません。
即日解雇の必要性はあるのか
また、これは解雇予告除外認定全体にいえることですが、そもそも即日解雇である必要があるのかは検討すべきでしょう。
即日解雇の場合、解雇予告手当を支払う必要があるので、その分の手当を支払わずに済むように解雇予告除外認定を行うというのが流れだと思いますが、そうではなく30日の解雇予告期間を設ければ、解雇予告手当を支払うことなく、解雇予告の義務を果たすことができます。
1.6. 内定と解雇予告
行政(通達)の考え方
内定とは、始期付解約権留保付労働契約すなわち「勤務開始時期を明示し、企業にそれを取り消す権利を保留させる労働契約」と、法律および判例では解釈されています。
労働契約ということは解雇予告手当を支払う必要がある、というのが行政の立場です。
学説の立場
しかし、労働基準法では「試用期間14日以内の解雇」の場合、解雇予告手当を支払う必要ないともされています。
企業によっては内定後、試用期間を経た後に正式採用という流れの会社も少なくありません。
そうなると行政の通達のとおりにすると、実際に労働を開始していない内定期間に内定が取り消された場合は解雇予告を支払う必要があるのに、実際に勤務が開始されてからの14日間に解雇された場合、解雇予告を支払う必要がないというアンバランスな状況が生まれてしまうので、支払う必要はないのでは、という学説も存在しているのです。
通達および学説は、どちらも裁判所の司法判断ではないので、どちらが優先されるかは実際に裁判にならないとわからないのが現状です。どちらにしても内定を出した以上、それを取り消すような真似はできるかぎり避けるべきなのは確かです。
2. 「解雇予告」条文の必要性
解雇に関することは就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に当たります。
ただ、ここでいう「退職に関する事項」とは「任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項」をいい、解雇予告がここに含まれるかは曖昧なところがあり、実際、定めのない規定例もみられます。
解雇予告自体は規則に定めあろうとなかろうと、法律の内容のまま行うことになるものの、基本的には予告手続きの漏れがないよう規定を定めておいた方がいいと思われます。
3. 「解雇予告」条文作成のポイント
3.1. 規定自体はあまり工夫しようがない
解雇予告に関する就業規則の条文については、法律の内容をそのまま書けばほぼ問題なく、会社ごとに大きく変える必要性の低いものとなります。
一応、法律よりも条件を下げることはできなくても手厚くすることはできるので、手厚くする方向で変更することはできなくもありませんが、そのようにする会社側のメリットはほぼないでしょう。
4. 就業規則「解雇予告」の規定例
第○条(解雇予告)
- 前条の定めにより、従業員を解雇するときは、解雇の日の30日前までに本人に予告し、予告しないときは平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。ただし、次に掲げる者を除く。
① 試用期間中であって、採用後14日以内の者
② 日々雇用される者(1か月を超えて雇用される者は除く)
③ 2か月以内の期間を定めて雇用する者(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
④ 懲戒解雇され行政官庁の認定を受けた者 - 天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合における解雇で、行政官庁の認定を受けたときは、前項の規定は適用しない。
- 1項の予告日数は、予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
5. 「もっと規定例を知りたい」「自分の会社に合った就業規則がほしい」方はこちらも!
目指したのは就業規則の参考書ではなく「英会話集」。
就業規則作成・書換のテクニック(出版社:日本法令 著者:川嶋英明)なら、多彩な規定例から会社の実態に合った規定を選ぶだけで、あなたの会社に合った就業規則が作成できます!
6. 解雇予告と関連のある条文別ポイント