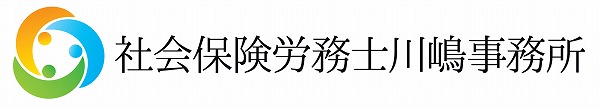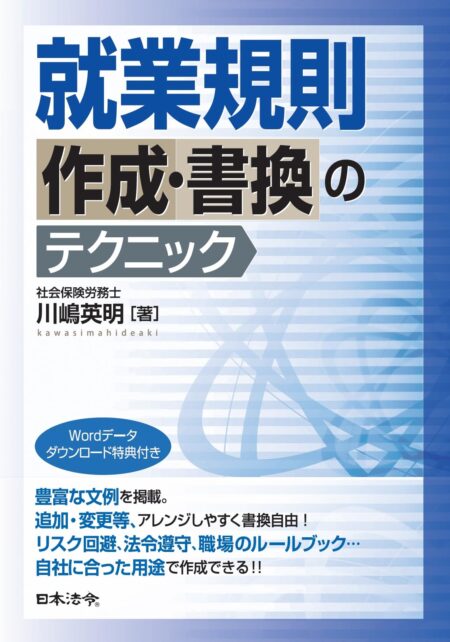会社を長年経営していると「この労働者を解雇したい」と思う瞬間があるのではないでしょうか。
しかし、よく知られているように、日本では解雇は簡単ではありません。
そして、それは小手先の就業規則の規定の工夫でなんとかできるものでもありませんが、規程でやれることがまったくないわけでもありません。
この記事では、そんな解雇について、そもそも解雇とは何か、なぜ解雇規制は厳しいのかといった点を押さえつつ、就業規則の規定例とそのポイントをみていきます。
この記事の目次
1. 法令から見た「解雇(普通解雇)」のポイント
1.1. 解雇は会社側による労働契約の解約
解雇とは、会社による労働契約の解約をいいます。
労働契約の解約については、民法において「解約の申込み後2週間の経過によって終了する」とされています。
これは労使双方、どちらからの申出であっても同様です。
しかし、会社側と比較して労働者側の立場が弱いことや、急な解雇による生活への打撃が大きいことから、民法を上回る規制として、労働法によって、解雇に関して様々な規制が行われています。
1.2. 解雇の種類
では、労働法における解雇規制とは具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。
その解説の前に、まずは解雇には種類があることを押さえておいた方がわかりやすいので、以下にその種類挙げておきます。
普通解雇
病気や怪我などの私傷病により業務遂行が困難な場合や重大な経歴詐称があった場合、労働契約を完全な形で履行することはできません。
そうした契約不履行による契約の解除を一般に普通解雇といいます。
また、労働者の職場規律の違反行為を行う者に対して、懲戒処分の代わりに普通解雇を行う場合もあります。
整理解雇
経営上の必要性、つまり、会社の経営不振によるリストラや体制の変更等のため行われる解雇のことをいいます。
この整理解雇は、普通解雇に含むのが一般的です。
この整理解雇を行う場合、以下の4つ要件(整理解雇の4要件)を満たす必要があります。
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力
- 人員選定の合理性
- 解雇手続の相当性
ただし、近年の裁判例でいうと、上記の4要件をすべて満たす、というよりは4要件について総合考慮して、その合理性や社会通念上相当かどうかを判断する傾向にあります。
懲戒解雇(諭旨解雇含む)
懲戒解雇とは、会社の服務規律に違反するなどした労働者に対する罰として行われる解雇をいいます。
この懲戒解雇は、普通解雇・整理解雇と分けて考え、就業規則の条文も別扱いとするのが一般的です。
そのため、懲戒解雇については別の記事で解説しています。
1.3. 労働契約法による解雇規制
ここからは解雇に関する法規制について解説を行っていきます。
まずは、労働契約法です。
労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」としています。
客観的に合理的な理由
つまり、解雇にはまず「客観的に合理的な理由」が必要ということですが、では、ここでいう「客観的に合理的な理由」とはなんでしょうか。
菅野労働法(第十二版)では、大きく以下の4つに大別できるとしています。
- 労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失(債務不履行)
- 労働者の職場規律の違反行為(懲戒解雇の代わりとして行われる解雇)
- 経営上の必要性に基づく理由(整理解雇)
- ユニオンショップ協定に基づく組合の解雇要求
見てわかるとおり、1と2は、上の普通解雇の項ですでに述べた内容です。
また、3は整理解雇のことをいいます。
4については、この記事を読まれる方で対象となる会社がほぼないと思われるため、解説を省略します。
社会通念上相当かどうか
上記のような「客観的に合理的な理由」があるだけでは、解雇は認められません。
合理的な理由があったとしても、それに対する解雇という措置が「社会通念上相当」でないと認められないからです。
例えば、整理解雇の場合、整理解雇の4要件を総合考慮して、客観的に合理的な理由があるか、社会通念上相当かどうかを判断します。
この基準については、過去の裁判例と比較してどうか、というところを注意深く調べていく必要があり、時には専門家のアドバイスを聞くことも重要となります。
いずれにせよ、裁判所は基本的には解雇に対して厳しい姿勢で挑むことが多く、「日本の解雇規制は厳しい」と言われる所以ともなっているので、生半可な内容では認められないと考えた方が良いでしょう。
1.4. 労働基準法による解雇制限
労働基準法では、以下の期間について、会社が労働者を解雇することを禁止しています。
- 業務上の怪我や病気の治療のために休業する期間とその後30日間
- 女性労働者の産前産後の休業期間とその後30日間
これらは労働者が、労災にあった場合の療養や、産前産後の休業を安心して行うための制限となります。
なお、業務災害による療養の場合については、例外的に、療養開始から3年を経過しても傷病が治らない場合に行うことができる「打切補償」を支払った場合、解雇することが可能となります。
また、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が困難となった場合」で、行政官庁の認定がある場合、上記の2つの期間中でも解雇は可能です。
1.5. 解雇の際には解雇予告が必要
解雇予告とは解雇の日の30日前の予告、もしくは平均賃金の30日分の予告手当を支給することをいい、解雇を行う際は会社の義務として、労働基準法に定められています。
この30日前の予告と予告手当の支給は併せて行うことも可能で、例えば、10日分の予告手当を支給する場合、20日前の予告で義務を果たすことができます。
この解雇予告はあくまで、解雇の手続き上の義務であり、これを行ったからといって、解雇の有効性が認められるわけではないことには注意が必要です。
解雇予告について、詳しくは以下をご覧ください。
2. 「解雇(普通解雇)」条文の必要性
解雇は就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に当たるため、必ず規定する必要があります。
3. 「解雇(普通解雇)」条文作成のポイント
3.1. 規定自体はあまり工夫しようがない
解雇に関する就業規則の条文については、会社ごとに大きく変える必要性の低いものとなります。
整理解雇が行われるのはどんな業種でも事業の縮小や経営上の必要性のためでしょうし、普通解雇にしても労働契約という根本が大きく変わることはないので、その不履行となる内容が、会社ごとに変わる、ということもありません。
つまり、会社によって解雇事由が変わる、ということがほぼないため、条文の方も会社ごとに大きく変える必要がないわけです。
3.2. 包括規定を忘れない
解雇については規定の内容よりも、実際の運用の方が重要です。
ただし、規定が不十分だったり、余計なことが書かれいたりすると運用の方にも支障が出ます。
代表的なところでいうと、解雇事由の最後に「その他前各号に準ずる理由があるとき」といった包括規定がない場合。
こうした包括規定がないと、解雇事由に記載のない内容での普通解雇ができなくなってしまいます。
また、解雇事由に関しても「著しく」「再三にわたって」などの、余計な形容詞があると、一発アウトな事由が起こったときの解雇の妨げとなることがあるので、書かない方が無難です。
4. 就業規則「解雇(普通解雇)」の規定例
第○条(解雇)
次の各号のいずれかに該当する場合、従業員を解雇する。
① 事業の縮小その他やむを得ない業務上の都合があるとき
② 天災事変その他やむを得ない事情があるとき
③ 勤務態度が不良で就業に適しないと認められるとき
④ 能力が不足していて就業に適しないと認められるとき
⑤ 協調性を欠くなど、他の従業員に悪影響を及ぼすとき
⑥ 作業に誠意がないなど、他の従業員に悪影響を及ぼすとき
⑦ 職場の秩序を乱すなど、他の従業員に悪影響を及ぼすとき
⑧ 身体または精神の障害により業務に耐えられないと認められるとき
⑨ その他、会社の従業員として適格性がないと認められるとき
⑩ その他前各号に準ずる理由があるとき
5. 「もっと規定例を知りたい」「自分の会社に合った就業規則がほしい」方はこちらも!
目指したのは就業規則の参考書ではなく「英会話集」。
この本なら、多彩な規定例から会社の実態に合った規定を選ぶだけで、あなたの会社に合った就業規則が作成できます!