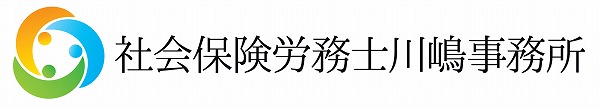この記事の目次
1. 自己都合退職とは
労働者が会社を辞める場合というのは、定年や解雇、契約期間の満了などいろいろありますが、そのほとんどは「自己都合退職」です。
自己都合退職とは、労働者側の都合による退職全般をいい、退職届ではよく「一身上の都合で」と表現されます。
入社した労働者がいつか会社を辞めるのは当然のこととはいえ、会社からすると、労働者に突然辞められると困ることが多いのも確かです。
今回は労働者の自己都合退職に関する労務管理について解説していきたいと思います。
2. 自己都合退職と法律上の定め
2.1. 自己都合退職は民法に定めあり
自己都合退職というのは、法的には労働者側からの労働契約の解除の申し入れとなります。
そして、労働契約の解除については、労働基準法上は特に定めはないものの、民法の627条では以下のように定められています。
第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
2.2. 労働者は2週間前の解約申し入れで解約可能
まず、1項の各当事者とは会社と労働者をいいます。
よって、会社と労働者、どちらからも「解約の申入れの日から二週間」が経過すれば、民法上は労働契約を解除できることになります。
ただし、会社側からの労働契約解約の申し入れというのは、いわゆる「解雇」の申し入れとなるため、この民法の規定を適用することはほぼ不可能となっています。なぜなら、解雇については労働基準法や労働契約法、その他判例で厳しい制限があるからです。
一方、労働者による解約の申し入れについては、それを制限する法律はありません。
つまり、労働者が希望すれば、退職の2週間前に、退職の意思を会社に伝えれば、会社を退職することができるわけです。
2.3. 完全月給制の場合は2項の規定を適用
ただし、「期間によって報酬を定めた場合」は同条2項の規定が適用されます。
「期間によって報酬を定めた場合」とは、いわゆる完全月給制がそれに当たります(同じ月給制でも、日給月給制の場合は1項を適用)。
ぱっと読むと民法627条2項に何が書いてあるかわかりづらいですが、要は、完全月給制の場合、解約の申し入れは賃金計算期間の前半にしないといけないということです。
例えば、完全月給制の労働者が4月20日に辞めたい場合、賃金計算期間の前半、つまり「3月21日から4月5日」のあいだにその申し入れをしないといけないわけです。
一方で「4月6日から4月20日」に退職の申し入れをした場合は、退職の時期は「5月20日」となります。
2.4. 2020年4月施行の民法改正にも注意
実はこの民法627条2項の規定は、2020年4月施行の改正民法で以下のように変更されます。
期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
追加された「使用者から」という文言により、先ほど見たような対応は会社からの解約申し入れに限られることになります。
つまり、完全月給制の労働者からの解約の申し入れであっても、賃金計算期間の前半に申し入れる必要はなくなり、他の労働者同様、2週間前の解約申し入れで労働契約を解除することができるようになるわけです。
就業規則の中には改正前の民法627条2項の適用を前提とした退職規定もあるので、その場合は改正法の施行前に、規則の改正をしておく必要があります。
2.5. 期間の定めのある労働者の自己都合退職
上記の民法の規定はあくまで「期間の定めのない労働者」についてでした。
では、契約社員のように期間の定めのある場合はどうかというと、上記の民法の規定は適用されません。
それどころか、契約期間途中の一方的な破棄は、労使どちらからであっても、契約違反となり、損害賠償の対象にすらなります。
とはいえ、契約社員が契約を一方的に破棄したいと言ってきたとしても、それによって会社が被る損害は金額にしてしまうとわずかなもの。それに割く時間や裁判費用の方がよっぽど高額となるでしょう。
そもそも、会社が労働者に対して損害賠償を請求しても認められない、認められても額はわずか、ということが多いので、実務上は「期間の定めのない労働者」と同じ扱いをすることがほとんどです。
3. 自己都合退職と就業規則と民法
3.1. 優先されるのは就業規則か民法か
さて、会社の就業規則には「退職の1ヵ月前までに」といったように、民法の2週間よりも長い期間が記載されていることがあります。むしろその方が一般的でしょう。
では、こうした場合、就業規則の規定と民法の規定、どちらが優先されるのでしょうか。
これは、労使間で合意があるかによって変わります。
3.2. 重要なのは合意の有無
というのも、民法というのは私人と私人のあいだで争いがある場合に適用される法律だからです。
会社と労働者も私人と私人ですから、労使間で争いがある場合は2週間が適用されるし、労使間で争いがない、あるいは労使間で合意が取れている場合は就業規則の規定が適用されます。
こうしたことから、就業規則や社内制度上、労使間で合意のある自己都合退職については「合意退職」、労使間で合意のない退職は「辞職」と分けているところもあります。
4. 自己都合退職と引継ぎの諸問題
4.1. 自己都合退職時の引継ぎで問題となる年次有給休暇
労働者が自己都合退職する際に、特に問題となるのが引継ぎです。
そして、引継ぎが問題となりやすい理由の一つが年次有給休暇の消化です。
会社としては、退職する前にきちんと引継ぎをしてほしいのに、労働者側が年次有給休暇を取得してしまうのでそれができなくなってしまうからです。
4.2. 退職時の年次有給休暇取得を会社は拒否できない
では、会社は引継ぎを理由に労働者の年次有給休暇取得を拒否できるかというと、これはできません。
会社は、労働者の年次有給休暇の時季指定権に対して、その時季を変更する時季変更権を持っています。
しかし、年次有給休暇は退職後に取得することはできないので、退職の決まっている労働者に関しては、時季を変更したくても、変更する日が残っていないわけです。
たまに、引継ぎができないと「事業の正常な運営を妨げる」と主張される方がいますが、そこは問題ではないわけですね。あくまで日程の問題が大きいわけです。
4.3. 年次有給休暇の買上
原則禁止の年次有給休暇の買上
それでも、どうしても引継ぎをきちんとしてほしいので年次有給休暇をしてほしくない、という場合は、年次有給休暇の買上で対応するのが現実的です。
年次有給休暇の買上とは、未消化分の年次有給休暇を会社がお金で買い取る制度をいいます。
この年次有給休暇の買上は、法律で原則禁止とされていますが、時効で消滅する分や、退職時に未消化の分については法律の規制がないので買上が可能となっています。
ただし、買上を強制することはできない
これを利用し、年次有給休暇を買い上げることによって、退職前に労働者に引継ぎをしてもらうわけです。
ただし、「買い上げるから年次有給休暇を取得するな」と強制することはできません。
あくまで退職する労働者に対して、引継ぎをしてもらうための交渉をするための制度と考えてください。
年次有給休暇の買上については過去に記事にしているので詳しくはそちらもご覧ください。
原則禁止の年次有給休暇の買い取りが可能となる3つの場合を解説
4.4. 退職前に必ず出社しないといけない日数を設定する
また、退職前に必ず出社しないといけない日数を設定する、という方法も一応はあります。
というのも、過去に「必ず出社しないといけない日数を設定し、その日数未満の出社しかしなかった場合、退職金を減額する」という規定が有効と認められた判例があるからです。
規定日数出社しなかった場合に「退職金を減額する」としているのがポイントです。
といのも、いかなる場合も、直接的に年次有給休暇の取得を禁止することはできません。一方、退職金であれば、法律上の規制がなく、会社の裁量の範囲が大きいので、会社の定める様々条件によって退職金を減額する、ということもできます。
よって、過去の判例にならって、上記のような規定を定め、引継ぎの日数を確保する、というのも1つの手ではあります。
ただ、筆者個人の考えとしては、上記の判例自体が昭和58年とかなり古い上、退職金の減額が間接的に年次有給休暇の取得を妨げているようにも思えるので、今後も同様の判断が行われるかは不透明に感じます。
5. 自己都合退職する労働者に対する会社の立場はとても弱い
ここまで、自己都合退職に伴う引継ぎを円滑に行うための制度をいろいろとみてきましたが、就業規則に何がどのように定められていても、労働者側が合意しない場合、2週間前の申し入れで会社を辞めることが可能であることを忘れてはいけません。
はっきり言ってしまうと、法律上、自己都合退職する労働者に対する会社の立場はとても弱いといえます。
このことを理解しないまま退職する労働者相手に居丈高に会社の都合を押しつけると、2週間前の解約を申し入れられた上、その2週間中、年次有給休暇の取得により一度も会社に出てこない可能性もあります。
そうなると、結局損害を被るのは会社です。
業務の引継ぎで損害を被りたくないのであれば、退職する労働者とよく話し合い、会社も時に妥協をしつつ、労働者の円満な退職のため支援する必要があるでしょう。
6. 自己都合退職の就業規則の規定例
最後に自己都合退職、というよりは退職に関する手続きの規定の例を紹介しておきたいと思います。
第 条(退職の手続き)
- 自己都合により退職するものは、14日前までに退職願を文書で提出し、承認あるまで従前の職務に服さなければならない。
- 退職(解雇も含む。)するときは、業務の引継ぎなど重要な事項を会社に報告しなければならない。
- 従業員は、退職しようとするとき(解雇されたときを含む。以下同じ。)は、退職日までに、健康保険証、その他会社からの貸付金品、又は会社に対する債務を直ちに返納、あるいは弁済しなければならない
- 会社は、従業員が退職したときは、権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。
退職の意思表明については、法律上は必ずしも文書で行う必要はなく、口頭でも有効となります。
一方で、規定例の1項のように「退職願を文書で」と就業規則にある場合は、文書で出さないと有効となりません。
退職時の言った言わない、特に後から「退職すると言ってない」というトラブルを避けるためにも、こうした一文を規定に入れておくのが安全でしょう。