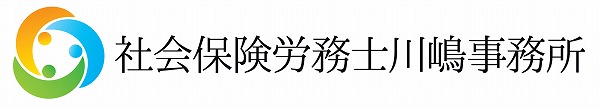こちらの記事の続き。
予告よりも間が空きましたが、今回は「インフルエンザ」について。
これから本格的に流行のシーズンに入るので、気をつけたいところです。
トネガワ本編では「限定ジャンケン」で忙しい中、インフルエンザの大流行で計画が危機に晒されますが、企業としてはインフルエンザに関する労務管理はどのようにするのが良いのでしょうか。
病気による欠勤の一般的なことは前回の記事で解説したので、今回はインフルエンザ特有の問題に焦点を当てたいと思います。
この記事の目次
1. 季節性のインフルエンザの法的な取り扱い
季節性のインフルエンザに関していうと、有名なのは学校保健安全法での取り扱いで、インフルエンザを発症した生徒は「発症後5日、解熱後2日」が経過するまでは出席停止となります。
なので、会社の労働者に関してもこれくらい休むことができる(労働者目線)、あるいは休ませることができる(会社目線)、と考えられそうですが、実は違います。
労働者が季節性のインフルエンザにかかった場合の法律的な決まりごとはなにもありません。
いやいや待て待てと、労働安全衛生法に「病者の就業禁止」という項目があるだろう、と思った人は社労士試験の受験生ですかね?(笑)
確かに、労働安全衛生法および労働安全衛生規則には以下のような定めがあります。
労働安全衛生法 第 68 条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令(※労働安全衛生規則 第 61 条のこと)で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない労働安全衛生規則 第 61 条 (病者の就業禁止)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
「伝染性の疾病」とか「病毒伝ぱの恐れのある伝染性の疾病」など、明らかに「インフルエンザ」のことを指している用に思えますが、確かに「新型インフルエンザ」や「鳥インフルエンザ」はこの中に含まれるのですが「季節性のインフルエンザ」は含まれていません。
つまり、冒頭で「インフルエンザ特有の問題」とか言いつつ、法律上はそんなものはないということになりました(汗)。
2. 病気でも働きたがる労働者はありがた迷惑
では、法律のことは置いておい場合の「インフルエンザ特有の問題」は何でしょうか。
それは伝染性の強い病気である点でしょう。
伝染性の強い病気のため、インフルエンザに感染している労働者を無理に働かせると他の労働者に感染する恐れもある。
なので、会社としては、基本的にはインフルエンザにかかっている労働者には、仕事の都合はあれど休んでもらいたい、と思うのが普通でしょう。あのブラック企業「帝愛グループ」ですらそうなのだから(笑)。
しかし、トネガワ本編ではインフルエンザを発症しているにも関わらず、休もうとしない黒服がひと波乱を起こします。
詳細は本編を読んでもらうことにして、こういうことをされると、正直会社としてはありがた迷惑。
では、こうしたときに会社はどのような対応をすればよいのでしょうか。
3. 本人に働く気があると休業手当が
問題となるのは、本人は働く気なのに、会社がその労働者を休ませようとするとなると「会社都合の休業」ということで休業手当が発生する点です。
まあ、正直、うつされたらたまったものではないのでお金を払ってでも休ませたい、という場合はこれでいいのかもしれません。
ただ、釈然としないと思う人が大半でしょう。
本人が自主的に休む場合(労働者の都合による休業)は無給なのに、とても働けそうにもないのに「働く意志がある」と主張するだけで、会社都合の休業となり休業手当が発生するわけですから。
4. 受診命令からの医師の判断
では、上記以外の方法で、労働者に休んでもらう方法はあるのでしょうか。
実は、医師の判断で休業させる場合、その責任は「医師」にあることになるため「会社都合」とはならず、休業手当は発生しません。
また、就業規則等に定めがある場合、会社が労働者に対して受診命令を出すこともできます。これがメンタルヘルスだと、考えないといけないことがまた増えますが、身体の病気に関しては特にありません。むしろ、放置するほうが「安全配慮義務違反」につながります。
なので、インフルエンザの疑いや、それ以外の場合でも風邪など体調が悪そうな労働者に対しては、病院への受診を勧め、医師の判断を仰いだほうが良いでしょう。